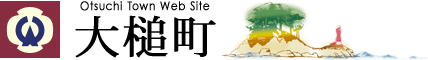磯焼け対策 Vol.1
磯焼けとは?
コンブやワカメなど大きな海藻がほとんど枯れてしまい、海の中の岩面が石灰藻で覆われ、白色または黄白色に変わってしまう「磯焼け」と言われる現象が広がっています。
磯焼けが広がると、大型海藻類の成長は悪化し、さらには海藻を餌としているウニやアワビの成長も悪化、藻場(海藻が生い茂っているようなところ)を産卵場所や育てる場所としている魚類も減少してしまいます。この状況が続いてしまうと海岸沿いに生息する魚介類が獲れなくなり、漁師や魚介類を原材料としている飲食店、食品加工場などにも大きな影響を与えてしまいかねません。
磯焼けが侵攻する原因は何か?
例えば、冬の時期でも海の水温が下がらないためウニの活動が活発なまま海藻を食べつくしてしまうこと。海の中の栄養が減少し海藻などの生きる力や繁殖する力が低下してしまうこと。海藻などを餌としているエビや小魚が食べ過ぎてしまう食害など、色々な原因があげられます。
そこで、町では昨年度(令和元年度)からダイバーの皆さんの協力のもと、船越湾内(吉里吉里)を中心として数カ所で水中のモニタリングや調査をしたところ、ウニの大量発生が大きな原因のひとつだと言うことがわかりました。
 |
 |
 |
このような状況から、町では、新おおつち漁業協同組合、NPO法人三陸ボランティアダイバーズなどの関連機関と協力し、大量発生しているウニの除去(移植放流、駆除など)、海藻類(コンブ、ワカメ)の植生活動を昨年(令和元年)から取り組んできました。
今年度(令和2年度)については、船越湾または大槌湾内の磯焼けの状況や海の中(現場)及び活動の様子などを町のホームページに掲載していきたいと思います。
 |
 |
 |