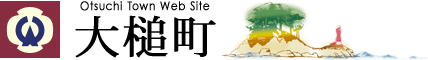子宮頸がんは、がんになる前の病変(異形成)が存在しているために、早期がんよりも早い段階で見つけられるのが特徴です。ごく稀に持続感染した一部のHPVウイルス(ヒトパピローマウイルス)が子宮頸がんに進行する可能性があります。 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) (PDF 5.77MB) 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) (PDF 7.17MB)
対象者
小学校6年~高校1年生相当の女子(12歳となり年度の初日から16歳となる年度末日までの間にある方)
標準的な接種年齢
中学1年生(13歳)となる年度の初日から末日までの間にある方
接種回数と間隔
サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類があり、接種するワクチンや年齢によって接種間隔が異なります。なお、原則として同じワクチンで規定回数を接種します。
- サーバリックス:計3回 初回接種から1か月後に2回目、初回接種から6か月後に3回目 ※上記の接種方法ができない場合は、初回接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、初回接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。
- ガーダシル:計3回 初回接種から2か月後に2回目、初回接種から6か月後に3回目 ※上記の接種方法ができない場合は、初回接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
- シルガード9(初回接種を15歳になるまでに接種の場合):計2回 初回接種から6か月以上の間隔をおいて2回目 ※上記の接種方法ができない場合は、初回接種から少なくとも5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。
- シルガード9(初回接種を15歳になってから接種の場合):計3回 初回接種から2か月後に2回目、初回接種から6か月後に3回目 ※上記の接種方法ができない場合は、初回接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
予診票
予診票(オレンジ色):中学1年生(13歳)となる頃に町から個別通知します。
※HPVワクチンは、平成25年6月14日付けの厚生労働省通知に基づき、積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日付けで同通知が廃止されたことに伴い、積極的な接種勧奨を行うことが決定しました。
キャッチアップ接種について
HPV ワクチンのキャッチアップ接種とは、積極的な接種勧奨の差し控えによりに接種を逃した方への救済措置として公費(無料)による接種機会を提供するものです。令和7年3月末日までに少なくとも1回以上接種していることを条件に、接種期間を令和8年3月31日まで延長して残りの回数分を接種することができます。
接種前には、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で接種してください。 HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します (PDF 572KB) 平成9年度~20年度生まれの女性でHPVワクチンを1回以上受けた方へ (PNG 355KB)
対象者
接種日時点で大槌町に住所があり、平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性のうち、令和7年3月末日までに少なくとも1回以上接種した方
予診票
紛失した場合は、健康福祉課で再発行が可能です。接種完了までに約4~6か月かかります。
その他
積極的な接種勧奨の差し控えにより定期接種を見送り、定期接種の対象年齢を過ぎてから自費で受けた方に対し接種を受けた回数分の費用を払い戻しします。以下の書類をご持参のうえ健康福祉課にて申請してください。 1 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの) 2 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用) 3 接種費用の支払いを証明するもの(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本のみ可 4 接種記録が確認できるもの(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し)
健康被害に対する救済制度
定期接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)