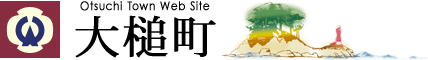経済的な事情や災害などにより保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の全額または一部の納付が免除または猶予される制度があります。
申請が遅れると、将来の老齢基礎年金だけではなく、障害の状態になったときや亡くなったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
未納のままにせず、お早めに手続きをしましょう。
申請免除
第1号被保険者で経済的な理由などにより保険料を納めることが難しいとき、次のいずれかに該当した場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
- 本人、本人の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の場合
- 申請者本人又は世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき
- その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等)
- 特別障害給付金を受けているとき
免除の区分
- 全額免除とは、保険料の全額が免除
- 4分の3免除とは、保険料の4分の3が免除(残り4分の1の保険料を納付)
- 半額免除とは、保険料の2分の1が免除(残りの2分の1の保険料を納付)
- 4分の1免除とは、保険料の4分の1が免除(残り4分の3の保険料を納付)
失業特例
失業された場合には、申請者の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除される特例措置があります。ただし、申請者が属する世帯の世帯主または配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。
承認されると
承認された期間は、全額免除の場合は将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されますが、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は免除されない残りの保険料を納めないと未納期間扱いになります。
また、受け取る年金額は、全額納めた場合に比べて少なくなります。
納付猶予
50歳未満(学生を除く)の国民年金第1号被保険者の方で、申請者及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」が設けられています。
次のいずれかに該当した場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 本人、本人の配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合
- 障がい者、寡婦の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合
- 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
- 失業により保険料を納めるのが難しい場合
- 震災・風水害・火災などで一定以上の損害を受けた場合
- 事業の休止または廃止により、総合支援資金貸付制度による貸付金を受けている場合
- 特別障害給付金を受けている場合
承認されると
承認された期間は、将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されます。
また、受け取る年金額には反映されません。
法定免除
第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが全額免除されます。
該当したとき、該当しなくなったときには届出が必要です。
- 国民年金や厚生年金、共済組合から障害(1級・2級)年金を受けている場合
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所など、厚生労働大臣が指定する施設に収容されている場合
承認されると
承認された期間は、将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されます。
また、受け取る年金額は、全額納めた場合に比べて少なくなります。
お手続き
次のものをお持ちになり、町民課国保年金係でお手続きください。
申請書は郵送で提出していただくことも可能です。
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
- 本人確認書類
注)特例認定区分で申請する場合、別途書類が必要になります。
保険料を納められるようになったとき
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある方は、老齢基礎年金(65歳から受ける年金)の受取り額が、保険料を全額納めたときに比べて少なくなります。
ただし、10年以内であればさかのぼって納付(追納)することができ、満額の年金額に近づけることが可能です。
なお、過去3年度より前の保険料を追納する場合は、当時の保険料のほかに一定の加算額が生じますので、お早めに追納することをおすすめします。
追納については、こちらをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)
関連情報
免除・納付猶予制度については、こちらもご覧ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
- 学生の方は、在学期間中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例」の対象となります。
- 国民年金第1号被保険者が出産したときは、「産前産後期間の免除制度」があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方への臨時特例措置があります。