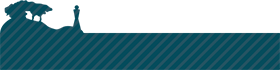大槌町復興推進隊持田専用ブログ

大槌町復興推進隊持田専用ブログ
【第3回】「イングレスをはじめる」
みなさんこんにちは!
大槌町復興推進隊の持田(もちだ)です。
突然ですが、なにかをはじめることに遅すぎることはないらしいですね。
あのケンタッキー・フライド・チキンを65歳で創業したというカーネル・サンダースも「人生は自分でつくるもの。遅いということはない。」と言っているそうですし…
ということで、今年はイングレスというゲームをはじめてみるのはいかがでしょうか?
イングレスをはじめるには、まず実際にやってみるのが一番!
そこで、スマホやタブレットにイングレスをインストールしてみましょう。
(※イングレスに対応するスマホやタブレットのOSのバージョンは、アンドロイドで4.0以上、iOSで7.0以上です。)
①まず、グーグルのアカウントを取得する。
「なぜ急にグーグル?」と思われる方もいるかもしれませんが、イングレスを作った「ナイアンティック」という会社は、グーグルから独立した企業という経緯からです。
すでにグーグルのアカウントを持っている人もイングレス用にアカウントをつくることをおすすめします。
イングレスのイベントなどに参加する場合、グーグルのアカウントを求められる場合が多くあり、わたくしのように本名で登録しているとプライバシーの問題も出てくる可能性があるからです。
②次に、スマホやタブレットにイングレスをインストールします。
アンドロイドなら「Google Play」、
iPhoneなら「App Store」のサイトからインストールしてください。
(iPhoneの場合、インストールする際にApple IDの入力を求められるので、IDとパスワードを事前に確認しておきましょう)
インストールができたら早速イングレスをはじめてみましょう。
最初に「コードネーム」を求められます。007的な感じでしょうか…
「コードネーム」といっても、ゲームの中で呼ばれる名前を自分で決めるだけです。
イングレスをしている人から「エージェント名なんですか?」と聞かれたら、この「コードネーム」のことです。
そう…イングレスをインストールした瞬間から、みなさんはFBIの捜査官やCIAの工作員のような「エージェント」になったのです!
③そして、所属する陣営を決めます。
イングレスには、シンボルカラーが緑の「エンライテンド」と青の「レジスタンス」二つの陣営があり、それぞれ自陣営が有利になるように「エージェント」として活動します。
どちらの陣営が正義や悪というわけではなく、ゲーム内で行うことも全く一緒です。
好きな色で選んでもいいですし、身近に「エージェント」の先輩がいればアドバイスを受けてもよいでしょう。
ちなみにイングレスの「エージェント」はスマホのことを「スキャナー」と呼びます。
もはや、みなさんのスマホは目には見えないイングレスの世界をスキャンする装置になったのです。
次回は、「スキャナー」と化したスマホを使って実際に「エージェント」活動を行います。
(つづく)
【第2回】「イングレスとは」
みなさん、こんにちは!
だいたい年始の決意は揺らぐものですが、おかげさまで2回目を迎えることができました。
大槌町復興推進隊の持田(もちだ)です。
第2回目はポケモンGOのお兄さん的な存在であるイングレスというゲームについて書きたいと思います。
ポケモンGOとイングレスは似ている部分も多いですが、当然のことながら違うゲームです。
簡単にイングレスを説明すると…
●世界1400万人以上が参加している人気スマホゲーム。
●日本はアメリカに次ぐ世界2位のプレイヤー数を誇る。
●プレイヤーは緑と青の陣営に分かれて、世界中の実際にある場所を舞台に「陣取り」をする。
●陣地となるスポットは実際にある名所や旧跡、建築、彫刻など。これを「ポータル」という。
●ポータルはプレイヤーがイングレスに申請する(現在は受付休止中)。
●ゲームをするために、プレイヤーは実際に現地のポータルに行かなければならない。
●ゲームをするプレイヤーが外に出るきっかけが生まれ、名所などをめぐる「まちあるき」になり、歩くので健康にもいい。
●「ミッション」というデジタルスタンプラリー機能を使えば、プレイヤーを観光コースに誘導する効果などが期待できる。
●観光や地域おこしのツールとして岩手県をはじめ多くの自治体に注目されている。
●初心者講習のような小規模なイベントから世界規模のイベントまで、様々なイベントが各地で開催されている。
●世界最大規模のイベントでは世界中から1万人以上のプレイヤーが参加する。
●日本ではローソンや伊藤園、ソフトバンクなど、企業とのタイアップによるキャンペーンが展開されている。
●地域の飲食店なども、自分の地域を訪れるプレイヤーに向けた独自サービスを展開している。
…これだけ見ると
「なんだか取っつきにくいゲームだな」と思われそうですが、イングレスは単純にゲームとして遊ぶだけではなく、柔軟に応用することができる「ツール」でもあります。
いろいろ書きましたが次回は、そのイングレスを実際にどうやってはじめるのか書きます。(つづく)
【第1回】「イングレスとポケモンGOとゲーミフィケーションと」
みなさん、あけましておめでとうございます!
大槌町復興推進隊の持田(もちだ)です。
新年を迎え、新たな取り組みとして、
これから12回にわたり「ゲーミフィケーション」をテーマにブログを書きたいと思います。
さて、年始ということで、初心を振り返っていたところ、
とても印象に残った言葉を思い出しました。
「今やこの地球上で週に30億時間以上がゲームに費やされているのです。」
(ジェイン・マクゴニガル著「幸せな未来は『ゲーム』が創る」より)
東日本大震災がおこった2011年。
当時、たくさんの人々が携帯電話ゲームに夢中になっていて、月に何十万円もプレイヤーがゲームに費やす、なんていう話もありました。
2012年5月、
いわゆる「コンプガチャ」について消費者庁が規制したことで一旦は収束しますが、そんなニュースを聞くたびに個人的には
「そんなに時間とお金があるなら、被災地のボランティアに行けばいいのに」
と思っていました。
その一方で「なにが人々をそこまでゲームに駆り立てるのだろう?」
「この行動力と時間とお金を使えば復興に役立てることができるのではないか?」と、興味も持っていました。
そんな時「ゲーミフィケーション」という考え方を知りました。
簡単に言うと「ゲームの力を活用して、課題の解決を図る」という考え方です。
例えば、交通の便が悪い場所があったとします。
交通の便が悪いので、行く人は少なく、景気もよくありません。
通常であれば、ただの不便な場所かもしれませんが、
ゲームに置き換えるとその不便な場所を「価値」に転換することができます。
ゲームのルールを
「交通の便が悪い場所に行けば行くほど、ポイントが加算される」
というようにすれば、ゲームをやっている人々にとっては、
あえて遠くて不便な場所へ行くことに意味を持たせることができ、そこに「価値」が生まれます。
ゲームの力により人々の行動をうながし、人々が移動することにより、交通費や食費、宿泊費などの経済効果が生まれる。
このような考え方が「ゲーミフィケーション」です。
昨年の7月にリリースされた「ポケモンGO」は爆発的にヒットしました。
11月には岩手県、宮城県、福島県の沿岸部に期間限定でレアポケモンが出現しやすくなった効果もあり、宮城県石巻市には期間中の11日間で約10万人が訪れたと言われています。
今でもレアなポケモンが出る場所には多くの人々が訪れています。
まさに「ゲーミフィケーション」の象徴でしょう。
ところで「ポケモンGO」は「イングレス」というゲームと切っても切れない関係にあることをご存知でしょうか?
「ポケモンGO」も「イングレス」も「ナイアンティック」という会社が作っています。
「ポケモンGO」の位置情報のノウハウやポケストップ、ジムなどは「イングレス」のデータをもとに作られています。
いわば「ポケモンGO」は「イングレス」の弟のような存在、という感じでしょうか。
「ポケモンGO」が爆発的にヒットする過程には「イングレス」が必要不可欠でした。
次回は、その「イングレス」について書きたいと思います。
【第1回】「イングレスとポケモンGOとゲーミフィケーションと」